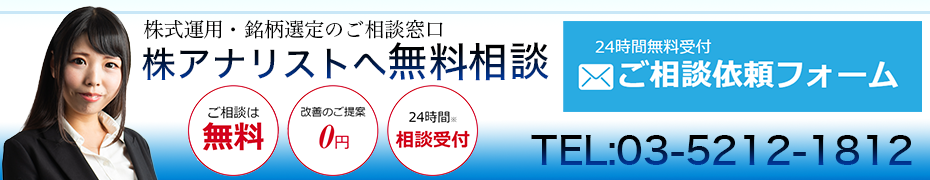【新NISA】成長投資枠では個別株を買うべき?大失敗を避ける方法も解説!
株式情報 投資戦略 2024.01.18

資産運用をサポートする制度であるNISAが2024年1月に改正され、新NISAへと変わりました。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があるため、つみたての枠はつみたてで活用できるけれど、成長投資枠はどう使おうと、考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、資産を効率よく増やすための成長投資枠の使い方と、注意点についてお伝えします。
目次
新NISAは儲かる?基本をプロが解説!
改正後の新NISAは、今までのNISAと比べてさまざまな点で変更があり、個人投資家のメリットが大きくなっています。
まずは、新NISAの基本をおさらいしておきましょう。
NISA制度を使うと、投資で得た利益に税金がかからない
NISA制度とは、投資で得られた利益にかかる税金が非課税になる制度です。
2023年までは、NISAには「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つの制度があり、それぞれ非課税で投資できる金額や投資できる商品、利用できる人などに違いがありました。
2024年から改正された新NISAは、これまでの「一般NISA」と「つみたてNISA」を統合した制度となります。
では、どこがどのように変わったのか?新NISAの変更点を確認します。
2023年までのNISAとの違い、新NISAの3つのポイントとは?

ポイント①:投資可能期間と非課税期間
1つ目のポイントは「投資可能期間」と「非課税期間」です。
今までのNISAでは、非課税期間が「つみたてNISA」で20年間、「一般NISA」で5年間となっていますが、新NISAでは、非課税で運用できる期間が無期限になっています。
今までのNISAでは投資できる期間が定められていました。しかし、新NISAでは制度が恒久化されたため、2024年以降はいつでも好きなタイミングで投資をすることができます。
ポイント②:年間投資枠
2つ目のポイントは、「年間投資枠」です。
新NISAのつみたて投資枠はこれまでの3倍となる120万円、成長投資枠はこれまでの2倍となる240万円に大きく増えています。
これまでのNISAでは、つみたてNISAと一般NISAの併用はできませんでしたが、新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、合計の年間投資枠は最大で360万円にもなります。
ポイント③:非課税投資枠の再利用
3つ目のポイントは、非課税投資枠が再利用できるという点です。
これまでのNISAの非課税投資枠は使い切りで、NISA口座で保有していた資産を売却しても非課税投資枠を再利用することができませんでした。
それに対し、新NISAでは、非課税投資枠の管理が投資元本ベースとなったため、新NISA口座で保有していた資産を売却して非課税投資枠に空きが出た場合、その空きを再利用して、翌年以降に非課税で投資することができます。
新NISAのポイントを簡単に説明しましたが、新NISAの移行によって個人投資家が得られるメリットは明らかに大きくなっています。
新NISAで資産を効率よく増やす方法は?

新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があります。
「つみたて投資枠」は、年間120万円を上限に、金融庁が定める長期の分散投資に適した投資信託につみたて投資を行える枠です。
「成長投資枠」は、年間240万円を上限に、投資信託だけではなく個別株にも投資を行える枠です。
投資枠の併用が可能になったことで、投資の自由度が上がったため、つみたて投資枠でコツコツ投資をしながら、個別銘柄に成長投資枠で投資するといった運用も行うことができます。
資産増加のカギを握るのは「成長投資枠」の使い方!
今回の新NISAで特に注目すべき点は、年間240万円まで投資可能な「成長投資枠」だと考えています。
なんといっても、NISA口座で買い付けた金融商品は非課税!
将来大きな成長が期待される企業に投資しておけば、株価が大きく上昇した際に、税務面で非常にお得と言えます。
「つみたて投資枠」では、インデックスファンドなどで長期的な資産増加を目指し、「成長投資枠」で成長性の高い企業に投資しておくことで、効率よく資産を増やすことができると思います。
新NISAで大失敗しないために、絶対に注意したいポイントとは?
ただし、「成長投資枠」を活用する上で1つだけ注意点があります。
それは、年間240万円までなら、1つの銘柄に集中投資ができてしまうという点です。
極端な話ではありますが、1つの銘柄だけに資金を集中させると、リターンと同時にリスクも大きくなります。
このため、投資の目的や目標額を設定したり、投資期間を考えたりと、個人の運用方針がより大切になります。
資産を取り崩す必要が出てくるのは何年後か、どのくらいの含み損なら耐えられるのかを考えて、計画性を持って投資を行うようにしましょう。
株式情報 投資戦略 2024.01.18

この記事を書いた人
日本投資機構株式会社 アナリスト日本投資機構株式会社 アナリスト
大学時代に投資家である祖母の影響で日本株のトレーディングを始める。大学時代、アベノミクスの恩恵も受けて、株式投資を投資金30万円で始め4年間で990万円まで資金を増やすことに成功する。卒業後、証券会社、投資顧問会社を経て2019年2月より日本投資機構株式会社の分析者に就任。モメンタム分析を最も得意としており、IPO(新規上場株)やセクター分析にも長けたアナリスト
アクセスランキング
- デイリー
- 週間
- 月間